日本の技術力の象徴とも言える新幹線。
その圧倒的な速さと、高い安全性は世界中から注目されていますよね。
「どうしてあんなに速いスピードで走れるのだろう?」
「あれだけ速いのに、なぜ脱線したりしないのだろう?」
そんな素朴な疑問を抱いたことはありませんか。
新幹線の滑るような高速走行と、揺れの少ない快適な乗り心地の裏には、数えきれないほどの技術と工夫が隠されています。
この記事では、新幹線がなぜあれほど速く、そして安全に走り続けることができるのか、その秘密を一つ一つ丁寧に解き明かしていきます。
私たちの知らない、驚くべきテクノロジーの世界を一緒に覗いてみましょう。
新幹線はなぜ風のように速く走れるの?驚異の高速走行を支える技術
日本の新幹線は、時速200kmを超えるスピードで都市と都市を結びます。
中には時速300kmを超える営業運転を行う車両もあって、まさに「弾丸列車」という名前にふさわしい速さです。
この驚異的なスピードは、決して一つの技術だけで実現されているわけではありません。
車両そのものの性能はもちろんのこと、線路や電気の供給、運行のシステムに至るまで、あらゆる要素が高速で走るために最適化されているのです。
それでは、新幹線が風を切って走るための具体的な秘密を、一緒に見ていきましょう。
スピードが出せる専用の線路!踏切なし、カーブもゆるやか
新幹線が速く安全に走るための大きな前提として、「専用の線路」で運行されている点が挙げられます。
私たちが普段利用する在来線のように、一般の道路と交差する踏切は一切ありません。
これにより、自動車や歩行者とのぶつかる心配がなく、列車はスピードを落とさずに走り続けることができるのですね。
線路のカーブも、在来線と比べてとてもゆるやかに設計されています。
急なカーブでは、速いスピードで走ると大きな遠心力がかかって、乗り心地が悪くなるだけではなく、脱線の危険性も高まってしまいます。
新幹線の線路は、できるだけまっすぐに、カーブがある場合でも半径を大きく取ることで、速いスピードで走る時でも安定した走行を可能にしているのです。
坂道についても同じで、急な坂はできるだけ避けられています。
これも、速く走る時のエネルギー効率や安定性を高めるための工夫と言えるでしょう。
このように、新幹線は「走るための環境」そのものが、高速走行に適した形で作られているんですね。新幹線の速さの秘密は、まずこの線路にあると言えそうです。
全車両にパワーを分散!強力モーターと「動力分散方式」の力
新幹線の車両が、あれほどスムーズに加速して、速いスピードを保ち続けられる秘密の一つに、「動力分散方式」という考え方があります。
これは、列車を動かすためのモーターを、編成されているたくさんの車両に分けて載せる方式のことです。
昔の機関車がお客さんを乗せた車両を引っ張る「動力集中方式」とは違って、それぞれの車両が自分で進む力を持つため、より効率的に大きなパワーを生み出すことができるんですよ。
この方式の良いところは、加速の性能が良いことだけではありません。
ブレーキをかける時にも、それぞれの車両のモーターを発電機として使って、電気ブレーキをかけることができるので、より強力で安定したブレーキ力を得られます。
一部のモーターに何か問題が起きても、他のモーターでカバーできるため、運行の信頼性が高いという利点もあります。
使われているモーター自体も、小さくて軽くて、しかもパワーのあるものが開発され続けていて、新幹線のさらなるスピードアップに貢献しています。
この「みんなで力を合わせて走る」という動力分散方式が、新幹線の力強い走りを支えているんですね。新幹線が速く走れるのは、この賢い仕組みのおかげでもあるのです。
軽くて丈夫な体!アルミニウム合金が支えるスピード
速く走るためには、車体そのものが軽いこともとても重要です。
車体が重いと、加速するのにもっと大きなエネルギーが必要になりますし、カーブを曲がる時やブレーキをかける時にも大きな負担がかかってしまいます。
そのため、新幹線の車体には、軽くて強度が高いアルミニウム合金がたくさん使われています。
アルミニウム合金は、鉄と比べて重さが約3分の1ととても軽いので、車体を大幅に軽くすることができるんです。
最初の頃の新幹線車両では鋼鉄製の車体も使われていましたが、より速く、よりエネルギー効率を良くしたいという要望が高まるにつれて、アルミニウム合金の採用が進みました。
もちろん、ただ軽いだけではお客さんの安全を守れませんよね。
そのため、ハニカム構造と呼ばれる蜂の巣のような形を取り入れたり、特別な押し出し成形という技術を使ったりすることで、軽さと強さを両立させています。
この軽くて丈夫な車体が、新幹線の俊敏な動きとエネルギー効率の向上に貢献しているのです。新幹線の速さには、この車体の軽さも一役買っているんですね。
空気の壁を切り裂く!流線形と見えない部分の工夫
時速300km近いスピードで走る新幹線にとって、「空気抵抗」はとても大きな壁になります。
スピードが上がれば上がるほど、空気抵抗は急激に大きくなって、走るためのエネルギーの多くが空気抵抗に打ち勝つために使われてしまうんです。
そのため、新幹線のデザインは、空気抵抗をできる限り減らすための工夫でいっぱいです。
一番わかりやすいのは、先頭車両のあの独特な流線形のデザインでしょう。
「カモノハシ」とか「アローライン」とか、時代や車両によっていろいろな形がありますが、どれも空気をスムーズに後ろへ受け流して、抵抗を減らすためのものなんです。
この形は、見た目の美しさだけではなくて、トンネルに入る時の大きな音(トンネルドンと言います)を小さくする効果も考えられています。
先頭車両だけではなくて、車両と車両の間の連結部分を覆うカバー(全周幌 ぜんしゅうほろ と言います)や、屋根の上にある電気を取り込む装置(パンタグラフ)の形、さらには床下にある機械をカバーで覆うなど、見えない部分にも空気抵抗を減らすための細やかな工夫が凝らされています。
これらの地道な努力の積み重ねが、新幹線のスムーズな高速走行を実現しているのですね。新幹線が速く走れるのは、こうした空気抵抗との戦いの成果でもあるのです。
目に見えないレールで安全確保!「ATC」という名の自動制御
どれだけ車両の性能が高くても、安全が確保されなければ速いスピードでの運転はできません。
新幹線では、「ATC(Automatic Train Control:自動列車制御装置)」という高度なシステムが、列車のスピードをいつも監視して、安全な運行を支えています。
ATCは、線路に設置された装置から列車の運転台へ、前にいる列車との距離やカーブ、坂道などの条件に応じて、走っても良い最高のスピードの情報を連続的に送ります。
運転士さんがその指示されたスピードを超えて運転しようとすると、自動的にブレーキがかかって、安全なスピードまで落とす仕組みになっているんです。
つまり、運転士さんのうっかりミスによるスピードの出しすぎを防いで、列車同士がぶつかったり、カーブでスピードを出しすぎて事故が起きたりするのを未然に防ぐことができるのですね。
このATCシステムは、新幹線が開業した当初から導入されていて、その後の技術の進歩とともに、もっときめ細かく、もっと安全性の高いものへと進化を続けています。
目に見えないこの「電子のレール」が、新幹線の安全な高速走行を根本から支えていると言えるでしょう。新幹線が脱線しない大きな理由の一つが、このATCシステムです。
新幹線はなぜ脱線しないの?高速でも揺れない驚異の安定性
新幹線に乗ると、その速さにも驚かされますが、同時に揺れの少なさ、乗り心地の良さにも感心させられますよね。
あれだけのスピードで走りながら、なぜ脱線することなく、安定した走行を保ち続けることができるのでしょうか。
そこには、線路(軌道 きどう と言います)と車両の両方に、日本の鉄道技術の粋を集めた様々な工夫が隠されています。
地震が多い日本ならではの対策も万全ですよ。
新幹線が脱線しないための、そして快適な乗り心地を実現するための秘密に迫ってみましょう。
レールが違う!揺らさないための軌道の秘密
新幹線が安定して速いスピードで走るための基礎となるのが、精密に管理された軌道(レール)です。
在来線では、短いレールを継ぎ足していくため、どうしても継ぎ目でガタンゴトンという音や揺れが発生しがちです。
しかし、新幹線では、数百メートルから時には1キロメートル以上にも及ぶ「ロングレール」が使われています。
これにより、レールの継ぎ目が大幅に減って、揺れや騒音が抑えられ、乗り心地が良くなるとともに、速いスピードで走る時の安定性も高まるんです。
レールを支える土台(道床 どうしょう と言います)にも工夫があります。
昔ながらの砂利を敷き詰めたバラスト軌道に加えて、コンクリートの板の上に直接レールを固定する「スラブ軌道」が多く採用されています。
スラブ軌道は、最初に作るのにお金はかかりますが、軌道のズレが少なく、メンテナンスの手間も減らせるので、長い目で見ると高速鉄道に適しているとされています。
これらの軌道は、「軌道検測車(きどうけんそくしゃ)」と呼ばれる特別な車両(ドクターイエローなどが有名ですね)によって、ミリ単位の細かさで定期的に検査されて、いつも最高の状態に保たれています。
この徹底した軌道の管理が、新幹線の安全で快適な走りを支える土台となっているんですね。新幹線が脱線しないのは、このしっかりとしたレール管理のおかげも大きいです。
車両の足元にも注目!高性能な台車とサスペンションの役割
新幹線の車両そのものにも、速いスピードで走る時の安定性を高めて、揺れを抑えるためのいろいろな技術が使われています。
特に重要なのが、車輪がついている「台車(だいしゃ)」の性能です。
速いスピードで走ると、ほんの少しの軌道のズレや横風などでも車体が左右に細かく揺れる「蛇行動(だこうどう)」という現象が起きやすくなります。
これを抑えるために、新幹線の台車には「ヨーダンパ」という油圧式のダンパーが取り付けられています。
ヨーダンパは、車体の左右の揺れを効果的に小さくして、乗り心地と走る時の安定性を良くします。
車軸を支える方法(軸箱支持方式 じくばこしじほうしき と言います)にも、速いスピードでの走行に適したものが採用されています。
車体と台車の間には、乗り心地を良くするための「サスペンション(懸架装置 けんかそうち と言います)」が備わっています。
最近の車両では、揺れをセンサーで感じ取って、コンピューター制御でサスペンションの硬さを調整して揺れを打ち消す「セミアクティブサスペンション」や、もっと積極的に揺れを抑え込む「フルアクティブサスペンション」といった高度な技術も導入されていて、まるで浮いているかのような滑らかな乗り心地を実現しています。
これらの足回りの技術が、新幹線の安定した高速走行を支える重要な要素となっているのです。新幹線が脱線しない、そして乗り心地が良いのは、こうした見えない部分の工夫があってこそなんですね。
地震大国日本の知恵!揺れを感知し、被害を食い止めるシステム
日本は世界でも有数の地震が多い国です。
速いスピードで走る新幹線にとって、地震はとても大きな脅威となります。
そのため、新幹線には、地震が起きた時に列車を安全に止めるための高度なシステムが備わっています。
その代表的なものが、「早期地震検知システム」です。
これは、地震の最初の小さな揺れであるP波(初期微動)を、線路の周りに設置されたたくさんの地震計でキャッチして、大きな揺れであるS波(主要動)がやって来る前に、電気を送る施設(変電所)に信号を送って列車の電気を止め、自動的に非常ブレーキをかけるというものです。
P波とS波が届く時間の差を利用することで、数秒から数十秒というわずかな時間ではありますが、列車を減速させたり止めたりするための貴重な時間を稼ぐことができるんです。
「ユレダス」やその後継システムである「テラス」などが知られています。
万が一脱線してしまった場合でも、被害をできるだけ小さくするための対策も行われています。
例えば、レールから車輪が大きく外れてしまうのを防ぐための「脱線防止ガード」が、特に地震の時に脱線の危険性が高いと考えられる橋の上やトンネルの中などに設置されています。
これらの地震対策は、過去の地震の教訓を活かして、絶えず改良が続けられており、日本の新幹線の安全性を語る上で欠かせない要素となっています。新幹線が脱線しないための備えは、地震に対しても万全なのです。
すべてを見守る司令塔!「CTC」による一元的な運行管理
新幹線の安全で効率的な運行は、「CTC(Centralized Traffic Control:列車集中制御装置)」と呼ばれるシステムによって、東京にある総合指令所という場所から一元的に管理されています。
指令所では、大きな表示盤に全ての線路の列車の位置や運行状況がリアルタイムで表示されていて、指令員の人たちがいつも監視しています。
電車のダイヤが乱れた場合の調整や、事故や災害が起きた時の素早い対応など、新幹線の運行に関わるあらゆる情報がここに集められて、ここから的確な指示が出されるのです。
このCTCシステムと、先ほどお話ししたATCシステムなどが連携することで、たくさんの列車が走っているにもかかわらず、とても高い時間通りの運行と安全性を両立させているんですね。
まさに、新幹線ネットワーク全体の神経の中心とも言える存在です。
まとめ 「新幹線の速さと安全性は日本の技術と知恵の結晶」
新幹線がなぜあれほど速く、そして安全に走り続けることができるのか、その秘密の一端をご紹介してきました。
専用の線路、強力なモーター、軽い車体、空気抵抗を減らすデザイン、そして高度な自動制御システム。
これら一つ一つの技術が、お互いに連携して、補い合うことで、あの驚異的なパフォーマンスが実現されているのです。
精密な軌道の管理、高性能な台車、万全な地震対策、そして一元的な運行管理システムが、日々の安全運行を支えています。
新幹線の速さと安全性は、決して偶然できたものではありません。
それは、たくさんの技術者さんたちの長い間の研究開発と、絶え間ない努力、そして日本の風土や社会の要望に応えようとする情熱が生み出した、まさに日本の技術と知恵の結晶と言えるでしょう。
次に新幹線に乗る機会があれば、その快適な乗り心地の裏にある、数々のテクノロジーに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
きっと、いつもの景色が少し違って見えてくるかもしれませんね。
【免責事項】
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
当サイトで掲載している料金表記について、予告なく変更されることがあります。






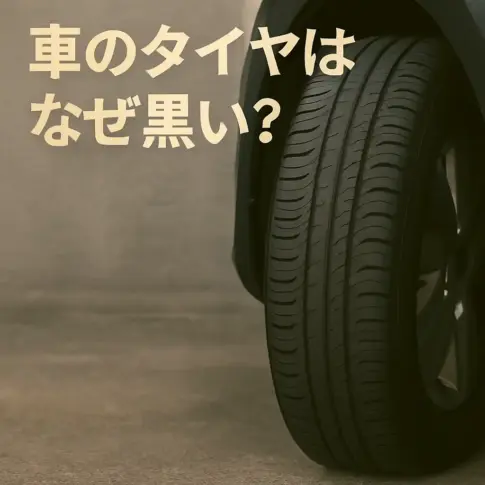


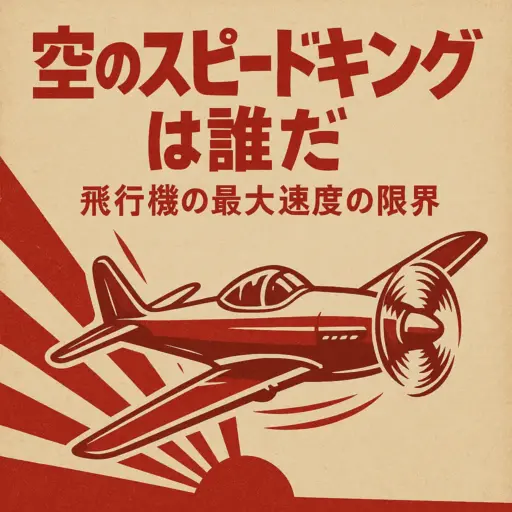
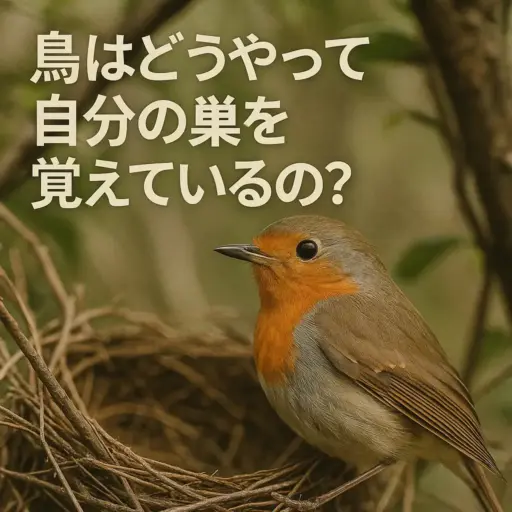

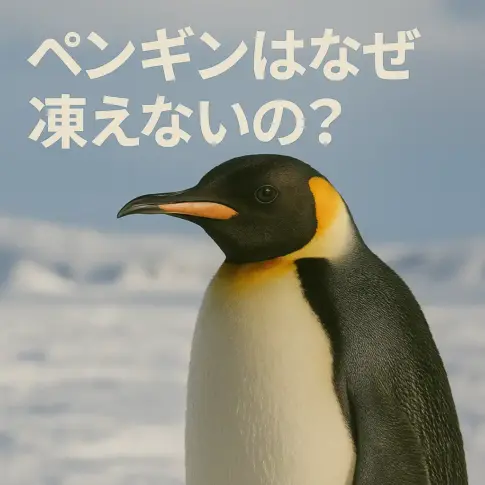
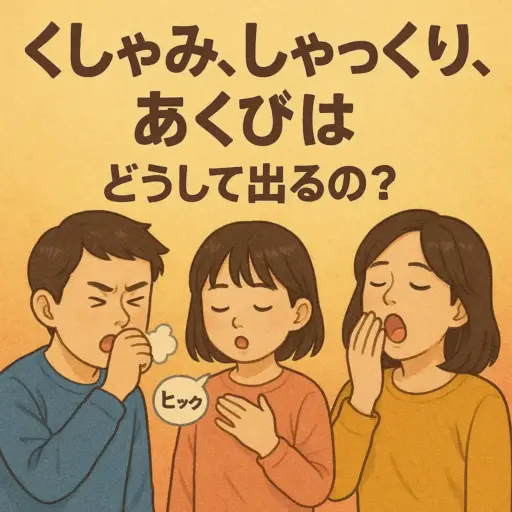
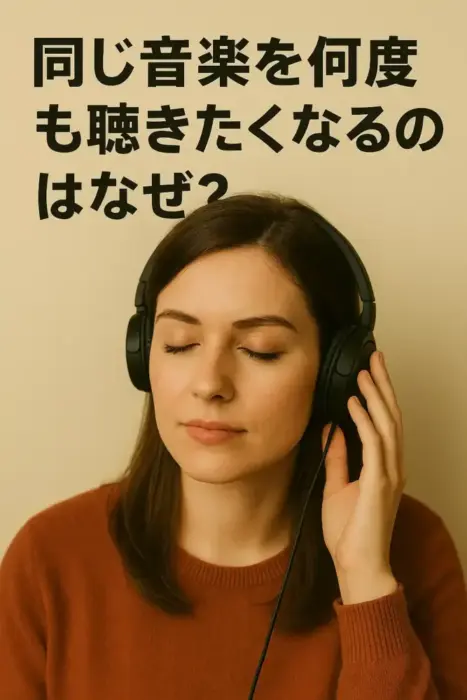

コメントを残す