大きな海を悠々と進む船。
特に、鉄でできた巨大な船が、どうして水にプカプカと浮いていられるのか、不思議に思ったことはありませんか。
「鉄の塊なのに、どうして沈まないんだろう?」
「何か特別な力が働いているのかな?」
実は、船が水に浮くのには、ちゃんとした科学的な理由があるんですよ。
この記事では、鉄でできた重い船でも水に浮くことができる、その不思議な力の秘密について、一緒にやさしく解き明かしていきましょう。
船を浮かせる魔法の力?「浮力」の正体を探る
船が水に浮くために、最も大切な働きをしているのが「浮力(ふりょく)」という力です。
この浮力とは、一体どんな力なのでしょうか。
そして、どうやって船を支えているのでしょうか。
船が水に浮く原理の中心には、この浮力の存在が欠かせません。
アルキメデスの原理って聞いたことある?水が物を押し上げる力
浮力の秘密を解き明かす鍵となるのが、「アルキメデスの原理」という法則です。
これは、今から2000年以上も昔の、古代ギリシャの科学者アルキメデスさんが発見したと言われています。
簡単に言うと、「水の中に入れた物は、その物がおしのけた水の重さと同じ大きさの力で、上向きに押し上げられる」というものです。
この上向きに押し上げる力が、まさに「浮力」なんですね。
お風呂に入ったとき、自分の体がお湯の中で少し軽くなったように感じませんか。
あれも、お湯が私たちの体を押し上げる浮力が働いているからなんです。
船も同じで、水に浮かんでいる船は、船がおしのけた水の重さと同じだけの浮力を、下から上へと受けているのです。
船の重さと浮力のバランスが大切!沈むか浮くかの分かれ道
物が水に浮くか沈むかは、その物にかかる「重力(地球が物を下に引く力)」と、「浮力(水が物を上に押し上げる力)」の大きさのバランスで決まります。
もし、物にかかる重力よりも、その物が生み出す浮力の方が大きければ、物は水に浮きます。
逆に、重力の方が浮力よりも大きければ、物は水の中に沈んでしまいます。
そして、重力と浮力がちょうど同じ大きさであれば、物は水中で静止するか、水面ギリギリで浮いている状態になります。
鉄の塊そのものを水に入れると、鉄の重さに対して、鉄がおしのける水の量が少ないため、浮力が小さく、沈んでしまいますよね。
しかし、船の場合はどうでしょうか。
鉄でできた船が沈まないのはなぜ?「形」に隠された秘密
鉄の塊は水に沈むのに、どうして鉄でできた大きな船は水に浮くことができるのでしょうか。
その答えは、船の「形」に隠されています。
船が水に浮くためには、この形がとても重要な役割を果たしているのです。
船の中は空っぽ?体積を大きくして浮力を稼ぐ工夫
船の形をよく見てみると、水面下の部分は大きく膨らんでいて、中は空洞になっていることが多いですよね。
これは、船全体の「体積(たいせき)」を大きくするための、とても大切な工夫なんです。
アルキメデスの原理を思い出してください。
浮力の大きさは、「物がおしのけた水の重さ」で決まります。
船の形を、水に浸かる部分が大きくなるように、つまり、おしのける水の量が多くなるように設計することで、より大きな浮力を得ることができるのです。
船の材料である鉄そのものは重いですが、船全体として見ると、内部にたくさんの空気を含んだ大きな「箱」のような構造になっています。
この大きな箱が、たくさんの水をおしのけることで、船全体の重さを支えるのに十分な浮力を生み出しているのですね。
コップを逆さまにして水に沈めようとすると、中に空気が残っている間は押し返されるような力を感じますよね。
あれも、空気が体積を稼いで浮力を生み出している一例と考えることができます。
船が水に浮くのは、この「体積を大きくして、おしのける水の量を増やす」という賢い工夫のおかげなのです。
船の「喫水線」って何?浮力と重力のバランスポイント
船の側面を見ると、水面と接するあたりに線が引かれているのを見たことがあるかもしれません。
これを「喫水線(きっすいせん)」と呼びます。
喫水線は、船が水にどれくらい沈んでいるかを示す線で、船が安全に航行できる限界の深さなども示しています。
船に荷物をたくさん積むと、船全体の重さが増えるので、その分だけ船は深く沈み込み、喫水線は上がります。
船が深く沈むということは、それだけおしのける水の量が増えるということなので、浮力も大きくなります。
そして、新しく増えた重さと同じだけの浮力が得られたところで、船は再び安定して浮くことができるのです。
つまり、船は常に「船全体の重さ」と「船がおしのけている水の重さ(=浮力)」が釣り合う深さで水に浮いているのですね。
この喫水線は、船が安全に浮いていられるための、とても大切な目印になっているのです。
船の安定性はどうやって保たれるの?揺れても元に戻る力の秘密
船は水に浮くだけではく、ある程度の波や風を受けても、ひっくり返らずに安定して航行できなければなりません。
この船の「安定性」または「復原力(ふくげんりょく)」も、船の設計において非常に重要な要素です。
船が傾いても元に戻ろうとする力は、どのようにして生まれるのでしょうか。
船の「重心」と「浮心」の位置関係が鍵
船の安定性を考える上で大切なのが、「重心(じゅうしん)」と「浮心(ふしん)」という二つの点の位置関係です。
「重心」とは、その物体の重さの中心となる点のことです。
船全体の重さが、この一点にかかっていると考えることができます。
一方、「浮心」とは、船がおしのけている水の体積の中心、つまり浮力が作用する中心点のことを指します。
船がまっすぐに浮いているときは、通常、重心は浮心よりも少し高い位置にあり、重心と浮心は船の中心線上に垂直に並んでいます。
傾いた船が元に戻る「復原力」の仕組み
では、船が波などで傾いた場合、どうなるのでしょうか。
船が傾くと、水に浸かっている部分の形が変わるため、浮心の位置が移動します。
多くの場合、船が傾いた側の低い方へ浮心が移動します。
すると、重力は変わらず重心に下向きにかかりますが、浮力は移動した浮心に上向きにかかるため、重心と浮心の間に「ずれ」が生じます。
この「ずれ」によって、船を元のまっすぐな状態に戻そうとする回転力(モーメント)が発生します。
この回転力が「復原力」と呼ばれるもので、船が傾きから回復する力となるのです。
船の底の方に重いエンジンを置いたり、バラスト水と呼ばれる重りの水を積んだりして、船の重心をできるだけ低く保つ工夫も、この復原力を高めるために行われています。
重心が低いほど、船は傾きにくく、また傾いても元に戻りやすくなるのです。
船が安全に航海するためには、この復原力が十分に確保されていることが不可欠なんですね。
まとめ 「船が水に浮くのは科学の法則と賢い設計のおかげ」
鉄でできた重い船が、どうして水に浮いていられるのか、その秘密が少しお分かりいただけたでしょうか。
船が水に浮くのは、アルキメデスの原理によって生じる「浮力」という上向きの力が、船全体の重さを支えているからです。
そして、船の形を工夫して、おしのける水の量を増やすことで、鉄の重さを上回る大きな浮力を得ているのですね。
さらに、船の重心と浮心の関係によって生まれる「復原力」が、船が傾いても元に戻ろうとする安定性を生み出しています。
一見すると不思議な船の浮遊も、実はちゃんとした科学の法則と、人間の長年の知恵と経験に基づいた賢い設計の賜物なのです。
次に港で大きな船を見かけたり、船に乗る機会があったりしたら、ぜひその船がどのようにして水に浮き、安定を保っているのか、この記事でお話ししたことを思い出してみてください。
きっと、船という乗り物に対する見方が、少し変わってくるかもしれませんね。
【免責事項】
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
当サイトで掲載している料金表記について、予告なく変更されることがあります。




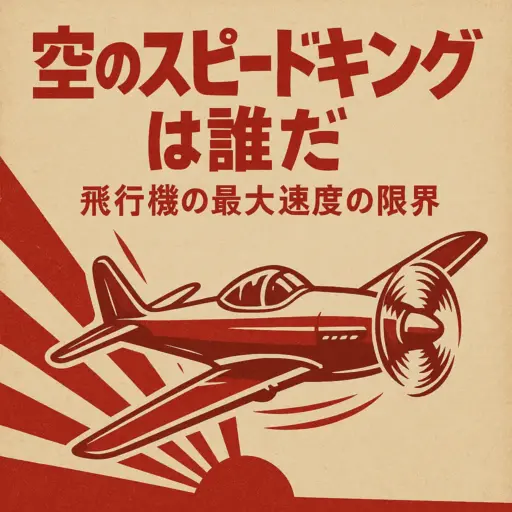




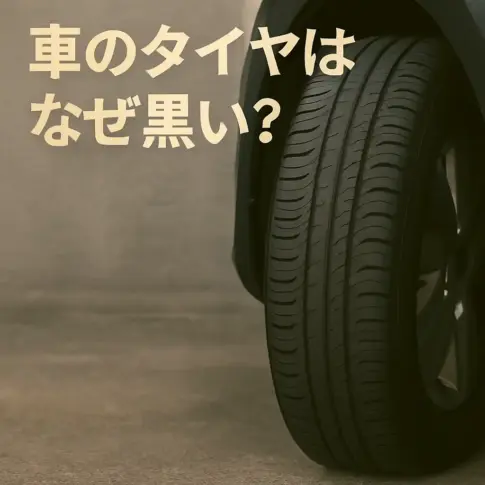


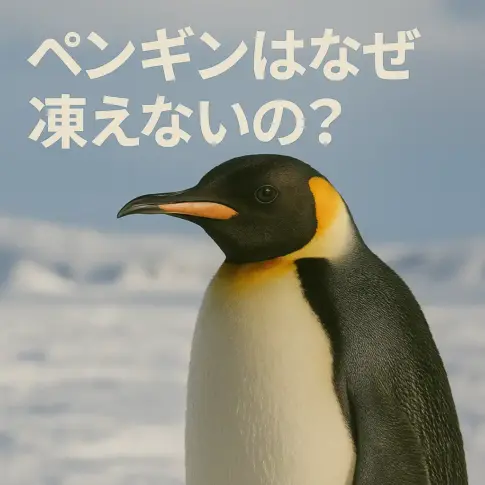
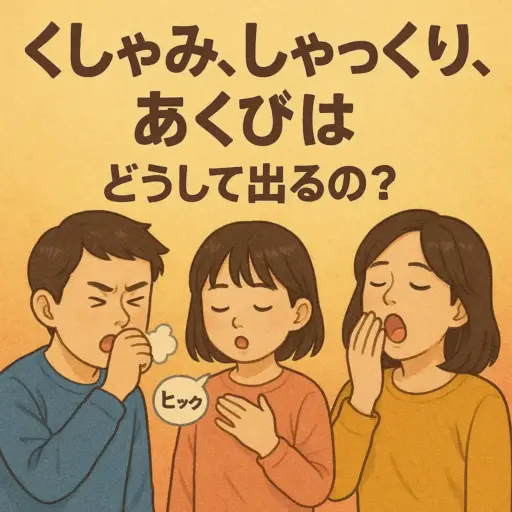
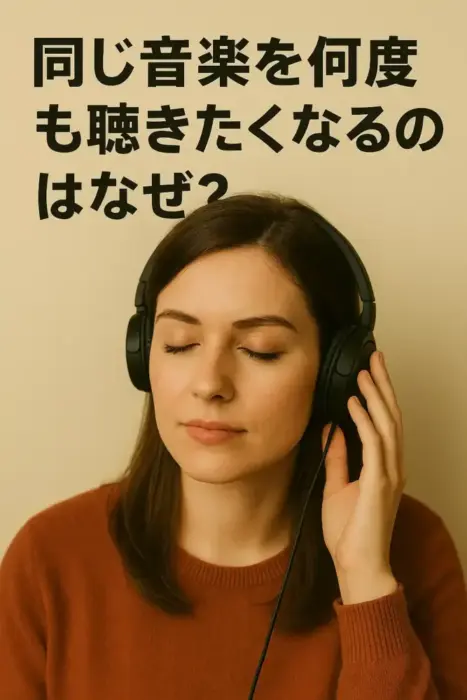

コメントを残す