インターネットを見ていると、
「世界一あたまの悪い生き物」なんていう話題が目に入ることがありますね。
特定の動物を取り上げて、
「なんだか賢くない行動をするなぁ」と感じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、科学的に見ると、ある一種類の動物だけを「一番あたまが悪い」と決めるのは、とても難しいことなんです。
むしろ、そういった見方は誤解を生みやすいとも言えます。
この記事では、なぜ単純に「あたまの良さ」で動物を順位付けできないのか、
そして「賢さ」って本当は何なのか、動物たちが持つ、驚くような生き残りの工夫について、
一緒に見ていきましょう。
「あたまが悪い」って誰が決めるの?評価の難しさ
私たちが普段、
「あの人はあたまが良い」とか「ちょっと苦手かも」なんて思うとき、
無意識のうちに人間の社会で大切とされる能力を基準にしていることが多いですよね。
例えば、問題を解決する力、新しいことを覚える力、記憶力、他の人と上手くコミュニケーションをとる力などです。
人間の物差しだけでは測れない動物たちの世界
この人間にとっての「ものさし」を、そのまま他の動物たちに当てはめてしまうと、実は大きな勘違いをしてしまう可能性があります。
動物たちは、それぞれが暮らす環境の中で、生き残り、子孫を残していくために、人間とは全く違う、独自の素晴らしい能力を発達させてきました。
人間の基準ではちょっと分かりにくいかもしれない、驚くような「知恵」を持っているんですよ。
ゆっくりだけど賢い?ナマケモノの生き方
例えば、「あたまが悪い」動物の代表みたいに言われがちなナマケモノについて考えてみましょう。
ナマケモノの動きは、確かにとてもゆっくりです。
一日のほとんどを木の上でじっとしているか、眠っているかで過ごします。
その姿だけを見ると、活発さとはほど遠く、「あまり賢くないのかな?」と思ってしまうかもしれません。
しかし、この「ゆっくり」な動きこそが、ナマケモノにとって最高の生き残り戦略なのです。
ナマケモノは、体のエネルギー消費がとても少ない、省エネな生き物として進化しました。
主食にしている葉っぱは、あまり栄養がないのですが、ゆっくり動くことで、使うエネルギーをできるだけ少なくしているんですね。
それに、あまり動かないことや、体に生えるコケのおかげで、敵に見つかりにくいというメリットもあります。
これは、ナマケモノが暮らす熱帯雨林という環境に、完璧にマッチした結果なんです。
人間の感覚で「怠けている」とか「鈍い」と判断するのは、少し違うのかもしれませんね。
ちょっと誤解されやすい?他の動物さんたちの例
ナマケモノ以外にも、「あたまが悪い」なんて言われてしまうことがある動物たちがいます。
ここでは、コアラとカカポを例に見てみましょう。
好き嫌いが激しい?コアラの特別な食生活
もう一種類、よく「あたまが悪い」と言われがちな動物にコアラがいます。
コアラはユーカリの葉っぱしか食べません。
しかも、そのユーカリの葉っぱには、他の動物さんにとっては毒になる成分が含まれています。
コアラは特定の種類のユーカリしか食べられず、栄養もあまり多くないため、エネルギーを節約するために、一日の多くを寝て過ごします。
体の大きさの割に脳が小さいとか、地面に落ちたユーカリの葉は食べ物だと認識できない、なんて話を聞くこともあります。
しかし、これもコアラが、ユーカリという特別な食べ物に特化して進化した結果なのです。
コアラの体の中は、ユーカリの毒を分解して、必要な栄養だけを取り出せるように、特別にできています。
食べられるものが限られているのは、確かにリスクもありますが、他の動物と食べ物を奪い合う必要がない、という良い点もあるんです。
コアラの生き方は、特定の場所で生き残るための、見事な工夫と言えるでしょう。
のんびり屋さん?カカポの置かれた状況
ニュージーランドに住んでいる、飛べないオウムのカカポも、「賢くない」と言われることがあります。
カカポは、もともと敵がいない安全な環境で進化してきたため、あまり警戒心が強くありません。
危険が近づいても、逃げずにじっと固まってしまうことがあるそうです。
人間や、後から持ち込まれた動物たちにとっては、残念ながら捕まえやすい存在となってしまい、今では絶滅の危機に瀕しています。
しかし、これはカカポが「愚か」だから、というわけではありません。
カカポが進化してきた環境では、じっとすることは必ずしも悪い選択ではなかったのかもしれません。
むしろ、他の鳥にはないユニークな子育ての方法を持っていたり、とても長生きだったりする、面白い特徴を持っています。
カカポが今、大変な状況にあるのは、環境が大きく変わってしまったこと、そしてそこに人間の活動が影響した結果が大きいのです。
カカポ自身の知能の問題として考えるのは、少し単純すぎるかもしれません。
動物の「賢さ」ってなんだろう?いろいろな物差し
そもそも、動物の「賢さ」って、どうやって測ればいいのでしょうか。
人間のIQテストみたいに、一つのテストで全ての動物の賢さが分かる、なんてことはありません。
動物の賢さは、その動物が生きていく上で解決しなければならない問題に合わせて、特別な形で現れるものなのです。
「賢さ」の形は一つじゃない
例えば、カラスやイルカ、チンパンジーたちは、道具を使ったり、難しい問題を解いたり、仲間から学習したりする能力が高いことで知られています。
これは、私たちが考える「賢さ」に近い部分かもしれませんね。
しかし、遠い距離を正確に旅する渡り鳥の能力や、ダンスで仲間とコミュニケーションをとるミツバチの能力、匂いを嗅ぎ分けたり人の気持ちを読み取ったりする犬の能力なども、それぞれの動物にとってはなくてはならない、立派な「賢さ」です。
サバンナで暮らすシマウマが、集団で模様を活かして敵の目をくらませるのも、魚の群れがぶつからずに一緒に泳ぐのも、高度な情報処理とチームワークに基づいた生き残り戦略であり、これも一種の「賢さ」と言えるでしょう。
環境への適応こそが本当の知恵
ある環境でとても役に立つ能力が、別の環境では全く役に立たない、ということもあります。
熱帯雨林で省エネ生活を送るナマケモノの戦略は、敵の多い草原では難しいでしょう。
逆に、草原を速く走れるチーターのスピードも、木の上ではあまり意味がありません。
それぞれの動物は、自分が生きる世界のルールの中で、一番良い方法を見つけ出し、進化させてきたのです。
まとめ「世界一あたまの悪い生き物」はいない、ということ
結論として、「世界一あたまの悪い生き物」というレッテル貼りは、科学的な根拠が乏しいと言えます。
動物たちの多様な生き方や能力に対して、少し失礼な見方かもしれません。
特定の動物の行動の一部だけを見て、「賢くない」と決めつけてしまうのは、私たち人間の偏った見方を押し付けているだけなのかもしれませんね。
私たちが大切にしたいのは、簡単にランキングをつけることではありません。
それぞれの動物が持っている、ユニークな生態や能力、そして、厳しい自然の中でどのように工夫して命をつないできたのかを、理解しようとすることではないでしょうか。
動物たちの世界は、私たちが思っている以上に奥が深く、驚きに満ちています。
いろいろな「賢さ」の形を知ることは、私たちの視野を広げ、地球という星の豊かさを改めて感じさせてくれるはずです。
ある動物が、人間の基準で見ると「賢く」見えなかったとしても、それは、その動物が自分の世界でしっかりと生きている証拠なのです。
免責事項
当記事は、動物の知能や生態に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の動物に対する評価を断定するものではありません。
動物の知能に関する研究は日々進んでおり、解釈は多様です。
掲載された情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性、安全性等を保証するものではありません。
当記事の情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。

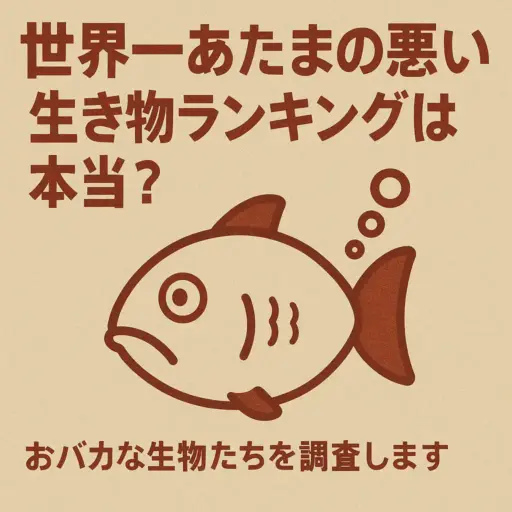

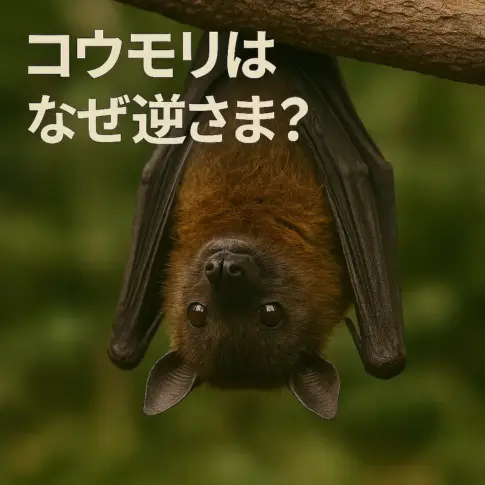
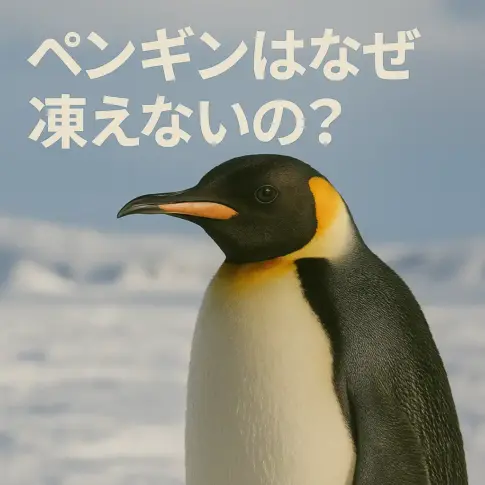

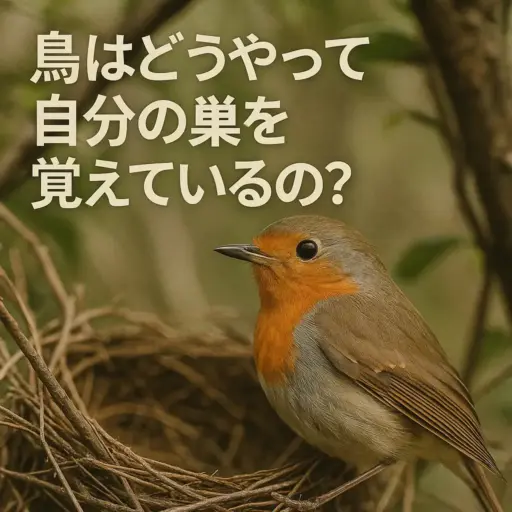

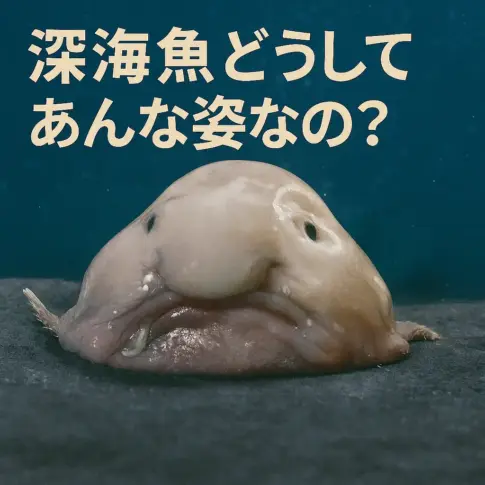


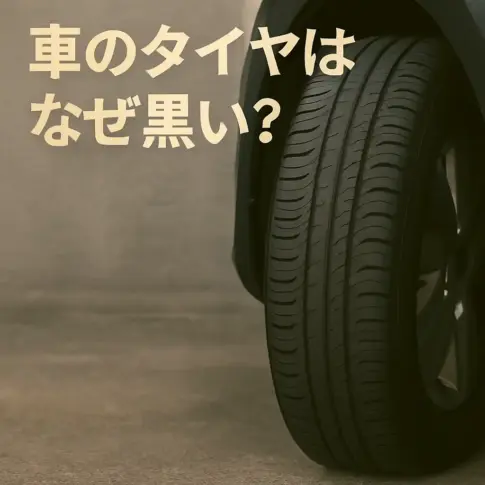



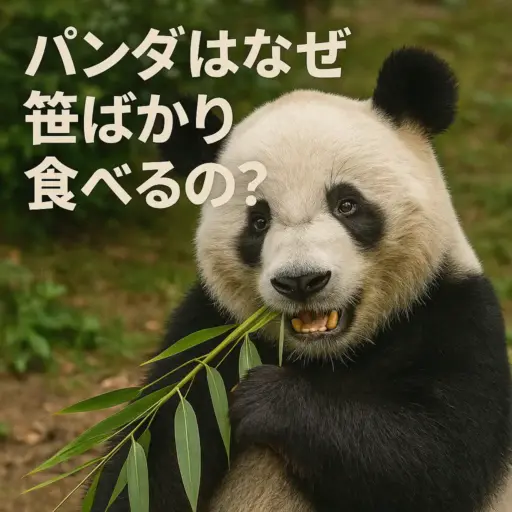

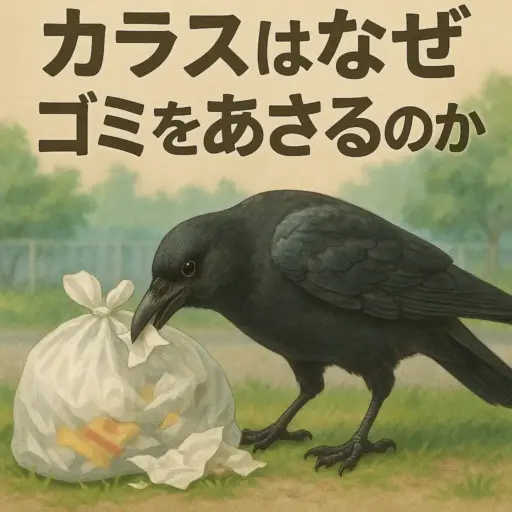

コメントを残す