空港で大きな飛行機が空へ飛び立つ姿、かっこいいですよね。
でも、あの何百トンもある鉄の塊が、どうして空を飛べるのか不思議に思いませんか。
実は、飛行機が空を飛ぶのには、ちゃんとした科学的な理由があるんです。
それは、「揚力(ようりょく)」「推力(すいりょく)」「抗力(こうりょく)」「重力(じゅうりょく)」という四つの力が、うまくバランスを取り合っているからなんですよ。
この記事では、この四つの力がどんな役割をしていて、どうやって飛行機を空に浮かべているのか、そのメカニズムを一緒に見ていきましょう。
飛行機を空に持ち上げる不思議な力「揚力」って何?
まず、飛行機が空に浮かぶために、一番大切な力が「揚力」です。
これは、飛行機をふわっと上に持ち上げようとする力のこと。
こんなに重い飛行機を持ち上げるなんて、一体どんな仕組みなのでしょうか。
飛行機が空を飛ぶ上で欠かせない揚力について、その秘密を少し探ってみましょう。
翼の形がポイント!空気の流れが生み出す魔法
揚力を生み出す大きな秘密は、飛行機の「翼(つばさ)」の特別な形にあります。
飛行機の翼の断面をじっくり見てみると、上の面が少しカーブしていて膨らんでいて、下の面は比較的平らなことが多いんです。
この翼の形が、空気の流れに面白い変化を起こします。
飛行機が前に進むと、翼は空気を分けるように進みますよね。
このとき、翼の上側を通る空気は、下側を通る空気よりもちょっとだけ長い道のりを、同じ時間で通ろうとします。
だから、翼の上側の空気の流れは、下側の空気の流れよりも速くなる傾向があるんです。
ここで、「ベルヌーイの定理」という、空気や水の流れに関する法則が関係してきます。
簡単に言うと、「空気みたいな流れるものは、スピードが速い場所ほど圧力が低くなって、スピードが遅い場所ほど圧力が高くなる」というもの。
翼の上側は空気の流れが速いから圧力が低く、下側は流れが比較的ゆっくりだから圧力が少し高くなります。
この翼の上と下で生まれる圧力の差が、翼全体を上に押し上げる力、つまり「揚力」になるんですね。
まるで、翼の下からたくさんの手で飛行機を支えているようなイメージです。
この翼の断面の形のことを「翼型(よくがた)」と呼んでいて、飛行機の種類や飛ぶ目的によって、いろいろな翼型が考えられています。飛行機が飛ぶ原理の中心には、この翼の働きがあるんですね。
翼の角度も大事!「迎角」で揚力をコントロール
翼の形だけではなくて、翼が空気に当たる角度も、揚力の大きさを変える大切なポイントです。
この、飛行機が進む方向の空気の流れに対して、翼がどれくらい傾いているかの角度を「迎角(むかえかく)」と言います。
一般的に、翼の迎角を少し上向きにすると、翼の下側により多くの空気が当たって、翼の上側では空気がもっと速く流れるようになるので、揚力は大きくなります。
飛行機が離陸する時や、もっと高く上がりたい時に、パイロットさんが飛行機の頭を少し上げるのは、この迎角を大きくして揚力を増やしているからなんですよ。
しかし、迎角を大きくしすぎると、翼の上側の空気の流れがバラバラになってしまって、翼から空気が離れてしまう「失速(しっそく)」という状態になってしまいます。
失速すると、揚力が急に無くなってしまうので、飛行機は飛んでいられなくなります。
だから、パイロットさんはいつも適切な迎角を保つように、とても慎重に飛行機を操縦しているんですね。飛行機が安全に飛ぶためには、この迎角の調整が欠かせません。
スピードがないと揚力も生まれない?速度との深い関係
揚力は、飛行機のスピードとも、とても深い関係があります。
実は、揚力の大きさは、飛行機のスピードの2乗に比例すると言われているんです。
つまり、スピードが2倍になると揚力は4倍に、スピードが3倍になると揚力は9倍になる、というわけ。
これが、飛行機が離陸する時に、長ーい滑走路を一生懸命加速していく理由です。
十分な揚力を得て、重い機体を地面から浮き上がらせるためには、それなりのスピードが必要になるんですね。
逆に、着陸する時にはスピードを落としていくので、揚力もだんだん小さくなっていきます。
こんなふうに、翼の形、迎角、そしてスピードという三つの要素がうまく組み合わさって、飛行機を空に浮かべるための揚力が生まれているんですね。飛行機が飛ぶ仕組みは、本当に奥が深いです。
前へ進むための力!「推力」を生み出すエンジンの働き
揚力が飛行機を上に持ち上げる力だとしたら、「推力」は飛行機を前に進ませるための力です。
この強い推力を生み出しているのが、飛行機のエンジンなんですね。
飛行機の種類によって、主にジェットエンジンとプロペラエンジンが使われています。
飛行機を前進させるこの力は、どうやって生まれるのでしょうか。
ジェットエンジンはどうやって推力を出すの?力強い噴射の秘密
今、大きな旅客機のほとんどがジェットエンジンを積んでいます。
ジェットエンジンの基本的な仕組みは、空気をたくさん吸い込んで、それをギュッと圧縮して、燃料と混ぜて燃やします。
その結果できる熱くて勢いのあるガスを、後ろへものすごい力で噴射するんです。
この時、「作用・反作用の法則」という理科で習う法則が働きます。
エンジンがガスを後ろへ強く押し出す「作用」に対して、ガスがエンジンを前へ強く押し返す「反作用」が生まれるんです。
この前へ押し返す力が、飛行機を前進させる推力になるんですね。
ジェットエンジンの内部は、前から順番に、大きなファン、空気を圧縮する圧縮機、燃料を燃やす燃焼室、圧縮機やファンを回すためのタービン、そして熱いガスを噴射するノズルという部分でできています。
これらの複雑な部品が、とても精密に連携することで、大きな飛行機を動かすほどの強い推力を生み出しているのです。飛行機のエンジンが生み出す推力は、空の旅に不可欠ですね。
プロペラ機の場合はどう?回転する翼が生み出す前進の力
一方で、小さな飛行機や一部の輸送機などでは、プロペラエンジンが使われています。
プロペラは、簡単に言うと、くるくる回る翼のようなものです。
プロペラの羽根一枚一枚も、飛行機の主翼と同じように翼の形をしていて、回転することで空気に対して揚力のような力を発生させます。
ただし、この場合の力は主に後ろへ空気を押し出す方向(または前へ空気を引き込む方向)に働いて、その反作用として飛行機を前進させる推力を生み出すんです。
扇風機が風を起こすのと少し似ていますが、プロペラの場合はもっとずっと強い力で空気を動かして、飛行機を引っ張っていくんですね。
エンジンの種類は違いますが、どちらも空気を使って前進する力を生み出している点では同じです。
空気の壁に立ち向かう!「抗力」との静かなる戦い
飛行機が空を飛ぶ時には、前に進もうとする推力に対して、それを邪魔しようとする力も働きます。
これが「抗力」、一般的には「空気抵抗」と呼ばれるものです。
飛行機を設計する人たちは、この抗力をどうやって小さくするかに、いつも頭を悩ませています。
飛行機のスムーズな飛行には、この抗力を減らす工夫が欠かせません。
飛行機の形はなぜツルっとしているの?形と空気抵抗の関係
空気抵抗にはいくつかの種類がありますが、まず思い浮かぶのが「形状抗力(けいじょうこうりょく)」です。
これは、物の形によって生まれる空気抵抗のこと。
例えば、平らな板を風に向けて立てるのと、先がとがった棒を立てるのとでは、明らかに平らな板の方が大きな抵抗を受けますよね。
飛行機の胴体や翼が、滑らかな曲線でできた「流線形(りゅうせんけい)」をしているのは、この形状抗力をできるだけ小さくするためなんです。
空気の流れをスムーズに後ろへ受け流すことで、空気の渦ができるのを抑えて、抵抗を減らしています。
機体の表面をできるだけツルツルにしたり、アンテナみたいな出っ張りをできるだけ少なくしたり、あるいはしまえるようにしたりする工夫も、抗力を減らすために行われています。
揚力を生むための代償?「誘導抗力」というもう一つの抵抗
実は、飛行機が揚力を生み出すこと自体が、別の種類の抗力を発生させる原因にもなるんです。
これを「誘導抗力(ゆうどうこうりょく)」と呼びます。
翼の上側と下側の圧力の差によって揚力が生まれる時、翼の端っこ(翼端 よくたん)では、圧力の高い下側から圧力の低い上側へと空気が回り込もうとする動きが起こります。
この回り込みによって、翼の端に空気の渦(翼端渦 よくたんうず)が発生するんです。
この翼端渦は、飛行機の後ろに引きずられるような力を生み出して、これが誘導抗力になります。
誘導抗力は、特にゆっくり飛んでいて大きな揚力が必要な時(例えば離陸する時や着陸する時)に大きくなる傾向があります。
最近の飛行機の翼の先が、上にクイっと曲がったような形(これを「ウイングレット」や「シャークレット」などと呼びます)になっているのを見たことがあるかもしれません。
あれは、翼端渦ができるのを抑えて、誘導抗力を減らすことで、燃費を良くするための工夫の一つなんですよ。
抗力との戦いは、飛行機の性能を良くするために、とても大切なことなんですね。
地球が引っ張る力「重力」とのバランスゲーム
そして、忘れてはいけないのが、地球上のすべての物にかかる「重力」です。
飛行機ももちろん例外ではなく、いつも地球の中心に向かって引っ張られています。
この重力に逆らって空中に留まり続けるためには、揚力がとても重要な役割を果たします。
飛行機が安全に飛ぶためには、この重力とのバランスをどう取るかが鍵となります。
重い機体を支えるために必要な揚力の大きさって?
飛行機が一定の高さを保って水平に飛んでいる時(巡航時)、翼が生み出す揚力と、機体にかかる重力は、だいたい釣り合っている状態にあります。
もし揚力が重力より小さければ飛行機は下がってしまいますし、逆に大きすぎれば上がってしまいます。
離陸して高度を上げていく時には、揚力が重力よりも大きくなるようにコントロールして、逆に降りて着陸する時には、揚力をだんだん減らして重力の影響を大きくしていきます。
あの何百トンもある大きな機体を支え続けるためには、それに見合うだけの強い揚力が必要で、それを生み出すための翼の設計やエンジンのパワーがとても大切なのです。
軽く作るための工夫!飛行機の材料と構造の秘密
重力に対抗するためには、揚力を大きくするだけではなくて、機体そのものをできるだけ軽く作ることも、とても重要です。
しかし、同時に、空中でかかるいろいろな力に耐えられるだけの強さも必要になります。
そこで、飛行機の材料には、軽くて丈夫なアルミニウム合金が長い間使われてきました。
最近では、もっと軽くて強度が高い炭素繊維強化プラスチック(CFRP)などの新しい材料も、機体の主要な部分に積極的に使われるようになっています。
これらの新しい材料は、今までの金属材料に比べて大幅に軽くすることができて、燃費を良くすることにも大きく役立っています。
機体の内部の骨組みにも、軽さと強さを両立させるための工夫がたくさん詰まっています。
例えば、ハチの巣のような六角形を敷き詰めた「ハニカム構造」は、とても軽いのにとても丈夫なので、床や壁などに使われています。
見えない部分にも、最新の技術がたくさん使われているんですね。
四つの力の素敵なハーモニー!飛行機が空を飛ぶということ
ここまで、揚力、推力、抗力、重力という四つの力について、それぞれ見てきました。
しかし、実際に飛行機が空を飛んでいる時には、これらの力がいつも複雑に絡み合って、バランスを取り合っています。
例えば、飛行機が離陸する時には、パイロットさんはエンジンをフルパワーにして最大の推力を得るとともに、フラップやスラットといった翼の補助装置を使って揚力を増やし、適切なスピードと迎角で機首を引き起こします。
上昇中は、推力が抗力と上昇に必要な力に打ち勝ち、揚力が重力と釣り合いながら高度を上げていきます。
一定の高度に達して水平飛行(巡航)に移ると、推力と抗力、そして揚力と重力がそれぞれ釣り合った状態で、最も効率よく長距離を飛行します。
目的地が近づき降下を始めるときには、エンジンの出力を絞って推力を減らし、スポイラーなどの装置を使って抗力を増やしたり、揚力を減らしたりしながら、安全に高度を下げていきます。
そして着陸時には、速度を十分に落とし、適切なタイミングで地面にタイヤを接地させます。
これらの各飛行段階において、四つの力を的確にコントロールし、安全かつ快適な飛行を実現するのが、パイロットさんの高い技術と経験なのです。
その背景には、航空力学という科学の法則と、長い間の人々の知恵と技術の積み重ねがあります。
まとめ 飛行機が空を飛ぶのは魔法ではなく科学と技術の結晶
飛行機がなぜあんなに重いのに空を飛べるのか、その秘密は、揚力、推力、抗力、重力という四つの力が織りなす、まさに素敵なハーモニーにあることが、少しお分かりいただけたでしょうか。
翼の形が生み出す揚力、エンジンが生み出す推力、空気の流れが作り出す抗力、そして地球が引く重力。
これらの目には見えない力が、高度な計算と設計に基づいてコントロールされることで、私たちは安全で快適な空の旅を楽しむことができるのです。
次に飛行機に乗る機会があったり、空を見上げて飛行機を見かけたりしたときには、ぜひこの四つの力のバランスに思いを馳せてみてください。
それは、人間の知恵と技術が自然の法則をうまく利用して実現した、まさに科学の結晶と言えるでしょう。
空を飛ぶという人類の長年の夢は、このような科学的な理解と技術の進歩によって現実のものとなったのですね。
【免責事項】
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。当サイトで掲載している料金表記について、予告なく変更されることがあります。





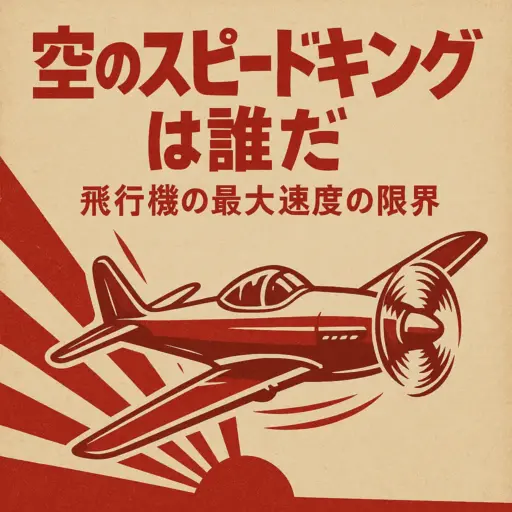


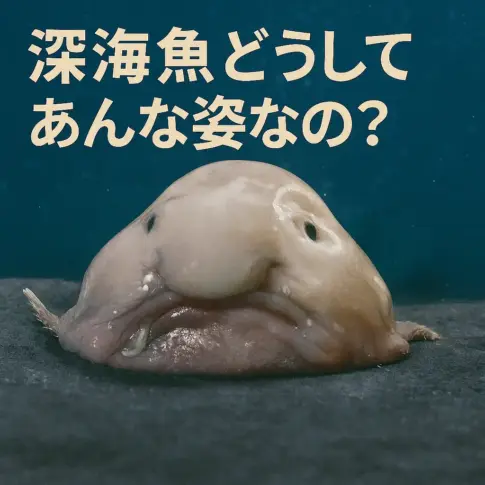

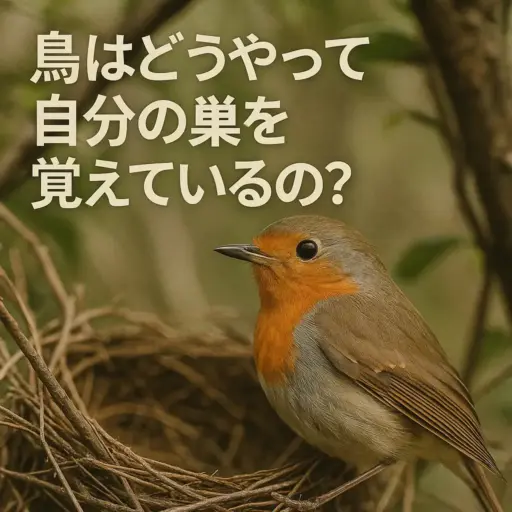
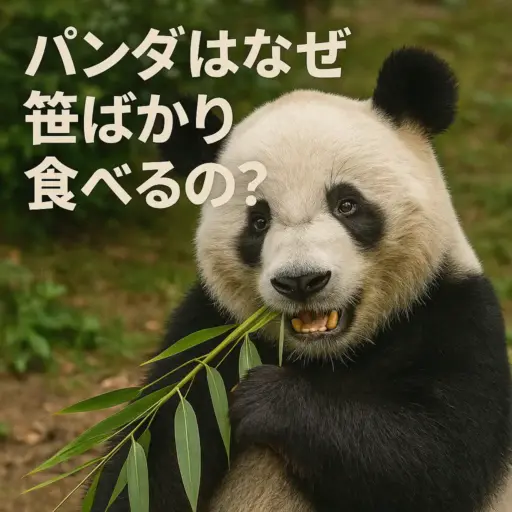
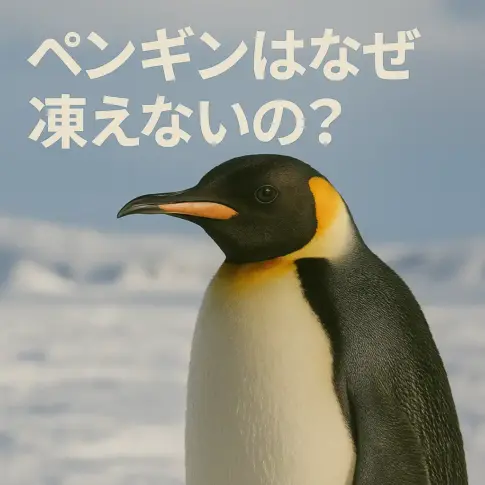

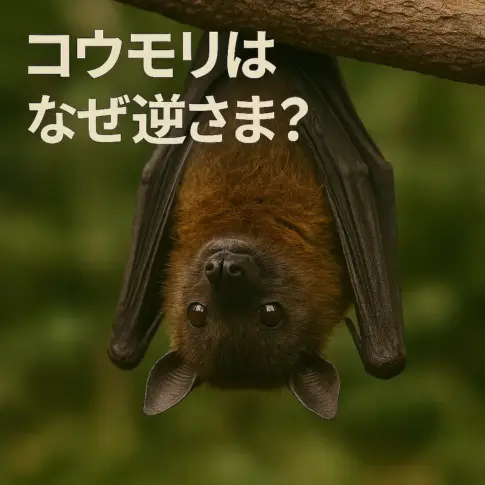
コメントを残す