こんにちは。
空を見上げたとき、どうして昼間の空はあんなに青いんだろうって思ったことはありませんか。
夕方になると、今度は空が真っ赤に燃えるように見えることもありますよね。
「空はなぜ青いの?」とか「夕焼けはなぜ赤いの?」って、不思議に思いますよね。
この記事では、そんな空の色の秘密について、一緒に見ていきましょう。
空の色が変わるのには、ちゃんと理由があるんですよ。
太陽の光の秘密を知ろう
まず、空の色を考える前に、太陽の光について少しお話ししますね。
太陽の光って、普段は白っぽく見えますよね。
しかし、その白い光は、実はたくさんの色が混ざってできているんです。
太陽の光の正体は虹の色
雨上がりに虹を見たことはありますか。
虹は、「赤(あか)、橙(だいだい)、黄(き)、緑(みどり)、青(あお)、藍(あい)、紫(むらさき)」といった、たくさんの色が並んでいますよね。
太陽の光も、プリズムという特別なガラスを通すと、虹と同じようにたくさんの色に分かれるんです。
つまり、太陽の光は、これらの色が全部合わさって白く見えているんですね。
光には色々な種類があって、色によって性質が少し違います。
青や紫の光は、たくさんのエネルギーを持っていると考えると分かりやすいかもしれません。
反対に、赤や橙の光は、少しおとなしい性質を持っています。
この色の違いが、空の色を決める大切なカギになるんです。
地球を包む空気「大気」ってなんだろう
次に、私たちの地球を包んでいる空気について考えてみましょう。
地球の周りには、目には見えないけれど、たくさんの空気があります。
この空気の層のことを「大気(たいき)」と呼びます。
もし、この大気がなかったら、空は真っ暗な宇宙と同じになってしまうんです。
昼間でも星が見えるかもしれませんね。
空に色がついているのは、この大気のおかげなんですよ。
空気の中には何があるの?
大気のほとんどは、「窒素(ちっそ)」や「酸素(さんそ)」という、とても小さなつぶつぶ(分子といいます)でできています。
私たちの呼吸に必要な酸素も、この大気の中にたくさん含まれています。
さらに、大気の中には、これらの小さなつぶつぶだけではなく、もっと大きなつぶ、例えば水のつぶ(水蒸気や雲のつぶ)、ちりやほこりなども浮かんでいます。
太陽の光は、宇宙からやってきて、この大気の中を通るときに、空気のつぶつぶにぶつかるんです。
この「ぶつかる」ということが、空の色を作り出す秘密なんですよ。
昼間の空はなぜ青いの? 空が青い理由を探ろう
さあ、いよいよ本題です。
どうして昼間の空は青く見えるのでしょうか。
それは、太陽の光が、大気の中の小さな空気のつぶつぶにぶつかることと関係があります。
光が空気のつぶつぶにぶつかると、光はいろいろな方向へ散らばっていきます。
これを「散乱(さんらん)」といいます。
青い光は散らばるのが大好き!
太陽の光には、虹のようにたくさんの色が含まれていましたね。
その中でも、青色や紫色の光は、エネルギーがあって活発な性質を持っています。
そのため、大気の中の小さな窒素や酸素のつぶつぶにぶつかると、とても強く、あちこちへ散らばっていくんです。
赤い光や橙の光は、あまり散らばらずに、まっすぐ進むことが多いです。
昼間、太陽が高いところにあるとき、青い光は空いっぱいに散らばります。
だから、私たちが空を見上げると、どの方向からも散らばった青い光がたくさん目に入ってくるんです。
これが、空が青く見える理由です。
高い山の上や飛行機から見る空が、地上で見るよりもっと濃い青色に見えるのは、空気が澄んでいて、青い光がよりきれいに散らばるからなんですよ。
でも、どうして紫色じゃないの?
ここで、「一番散らばりやすいのは紫色のはずなのに、どうして空は青く見えるの?」と思うかもしれませんね。
それは、いくつかの理由があります。
一つは、太陽の光に含まれる紫色の光の量が、青色の光よりも少し少ないこと。
もう一つは、私たちの目が、紫色よりも青色の方を感じやすいようにできていること。
これらの理由が合わさって、私たちの目には空が青く見えていると考えられています。
夕焼けや朝焼けはなぜ赤いの? 空が赤くなる仕組み
夕方になると、空の色がガラッと変わりますよね。
太陽が沈む地平線のあたりが、赤やオレンジ色に染まって、とてもきれいです。
朝、太陽が昇るときも同じように赤くなることがあります。
どうして夕方や朝方の空は赤くなるのでしょうか。
これも、太陽の光と大気の関係で説明できるんです。
太陽の光の長い旅
昼間は、太陽は空の高いところにあります。
だから、太陽の光は、大気の中を比較的短い距離だけ通って、私たちのところに届きます。
しかし、夕方や朝方は、太陽は地平線の近く、低いところにありますよね。
そうすると、太陽の光は、大気の中をとても長い距離、斜めに進んでこなければならなくなります。
赤い光だけがゴールできる!
太陽の光が、大気の中を長い距離進むとどうなるでしょうか。
散らばるのが大好きな青い光は、長い旅の途中で、あちこちに散らばってしまって、私たちの目に届く前にほとんどなくなってしまいます。
まるで、マラソンで途中で疲れてしまうような感じです。
しかし、赤い光や橙の光は、もともとあまり散らばらずにまっすぐ進む性質があります。
だから、長い大気の層を通ってきても、途中で力尽きることなく、私たちの目にまで届くことができるんです。
その結果、太陽の周りの空は、散らばらずに残った赤い光や橙の光で、赤く見えるというわけです。
これが、夕焼けや朝焼けが赤くなる仕組みなんですね。
日によって夕焼けの色が違うのは、空気中の水蒸気やちりの量などが違うからです。
ちりなどがたくさんあると、光の散らばり方がもっと複雑になって、よりドラマチックな色の夕焼けが見えることもありますよ。
白い空や雲の秘密 ミー散乱ってなに?
空の色は、青や赤だけではありませんよね。
空全体が白っぽく見える日もあります。
空に浮かぶ雲も、たいてい白く見えます。
これはどうしてでしょうか。
これには、これまでお話しした散乱とは、また別の種類の散乱が関係しています。
大きなつぶは色を選ばない
大気の中には、窒素や酸素のような小さなつぶだけではなく、雲をつくる水のつぶ(水滴)や氷のつぶ(氷晶)、大きなちりやほこりなど、比較的大きなつぶも浮かんでいます。
太陽の光が、これらの大きなつぶにぶつかると、青い光も赤い光も、ほとんど同じように散らばるんです。
色による散らばり方の違いがあまりないんですね。
太陽の光は、もともとたくさんの色が混ざって白く見えていました。
その光が、大きなつぶによって、どの色も同じように散らばると、散らばった後の光も、やっぱり白っぽく見えます。
これが、雲が白く見える理由です。
空気がちりやほこりで汚れている日や、湿度が高い日に空が白っぽく見えるのも、この大きなつぶによる散乱の影響が大きいからです。
まとめ 空の色の不思議な科学
空が青いのも、夕焼けが赤いのも、ちゃんと科学的な理由があったんですね。
まとめてみましょう。
昼間の空が青いのは、太陽の光の中の青い光が、空気の小さなつぶつぶによって、空いっぱいに散らばるからです。
夕焼けや朝焼けが赤いのは、太陽の光が大気の中を長い距離通ってくる間に、青い光は途中で散らばってしまい、散らばりにくい赤い光が私たちの目に届くからです。
雲やかすんだ空が白く見えるのは、空気中の大きな水のつぶなどが、太陽の光のすべての色を同じように散らばらせるからです。
普段何気なく見ている空の色には、こんな面白い科学が隠されています。
次に空を見上げるときには、ぜひ今日の話を思い出してみてください。
空の色の変化が、もっと面白く感じられるかもしれませんよ。
【免責事項】
この記事は、空の色に関する一般的な情報を提供することを目的としており、専門的な研究や学術的な正確性を保証するものではありません。
内容は、一般的な理解に基づき、分かりやすさを優先して記述しています。
特定の現象や詳細については、専門機関の情報をご参照ください。
この記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご了承ください。

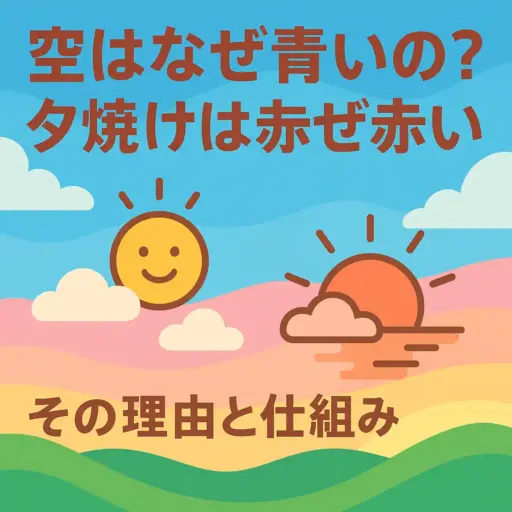
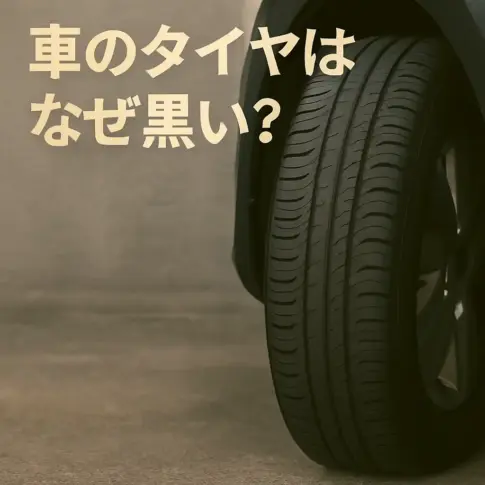




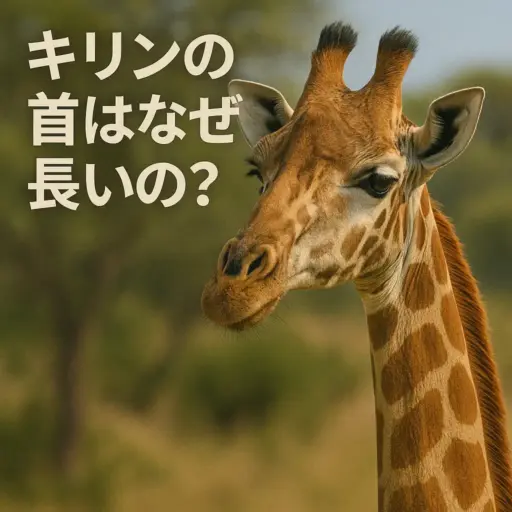
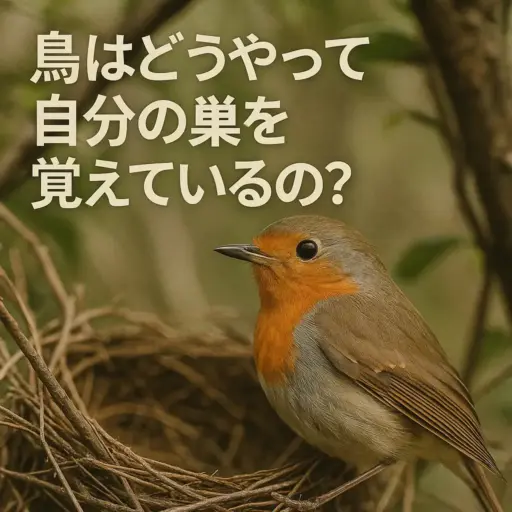
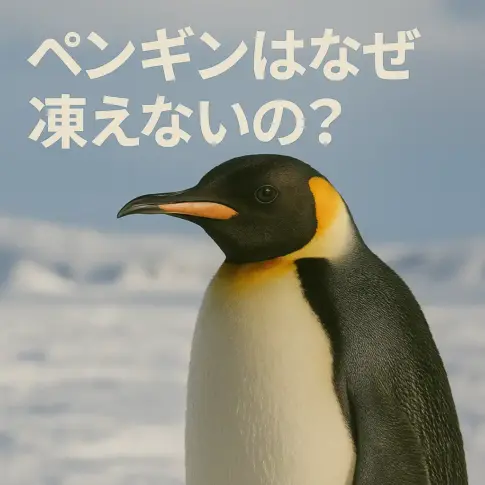
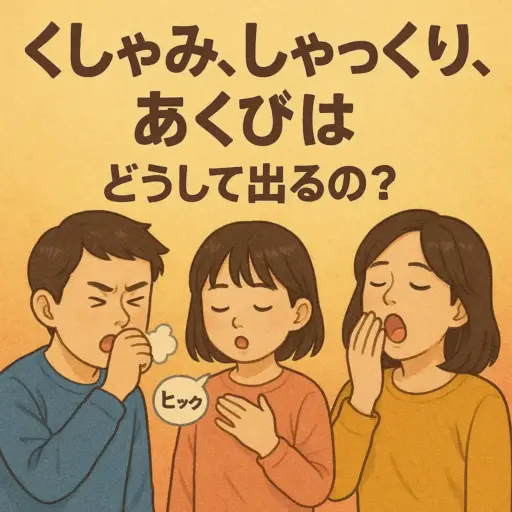

コメントを残す