普段、何気なく目にしている信号機の色。 赤、黄、そして青(緑)。
これらの色には、どんな意味が込められているのでしょうか。
どうしてこの3つの色が選ばれたのか、考えたことはありますか。
この記事では、そんな信号機の色にまつわる疑問をスッキリ解決します。
信号機が誕生した歴史的背景から、色が持つ科学的な根拠、日本で「青信号」と呼ぶ理由、さらには未来の信号機がどうなるのかまで、わかりやすくお伝えしていきますね。
きっと、この記事を読み終わるころには、いつもの信号機が少し違って見えるはずです。
信号機の始まりはいつ? 鉄道信号から道路へ 色が決まった歴史の旅
今の電気式信号機のご先祖さまは、実は19世紀のイギリスで生まれました。
産業革命が進んで、人や物がたくさん移動するようになった時代です。
特に鉄道がどんどん発達して、安全に列車を動かす仕組みが必要になったんですね。
最初の信号機はロンドンに登場! 赤と緑が選ばれたワケ
1868年、ロンドンの国会議事堂の前に、世界で初めてと言われる道路用の信号機が設置されました。
これは、鉄道の信号システムを道路交通に応用したものだったんです。
考案したのは、J.P.ナイトさんという鉄道技師の方です。
昼間は警察官の方が手で腕木を操作し、夜になると赤と緑のガス灯を灯していました。
このときから既に、「赤」は危ないから止まれ、「緑」は安全だから進め、という色の役割があったんですね。
では、どうして「赤」と「緑」が選ばれたのでしょうか。
「赤」が「止まれ」や「危険」を示すようになったのは、私たち人間が本能的に持っている感覚と深く関わっていると言われています。
炎や血の色である赤は、昔から危ないことや注意すべきことを知らせる色として認識されてきました。 科学的に見ても、赤色の光は波長が長くて、空気中のチリなどに邪魔されにくい性質を持っています。
だから、霧が出ている日や雨の日でも、比較的遠くまで色が届きやすいんです。 危ないことを知らせるには、とても合理的な色だったんですね。
多くの国で、昔から赤色は警告や禁止の色として使われてきました。
一方、「進め」を意味する緑色が選ばれた理由は、赤色ほどストレートではありません。
昔の鉄道信号では、「進め」を白い光で示すこともあったそうです。
しかし、白い光は街の灯りなどと見分けがつきにくくて、夜には間違えやすいという問題点がありました。
そこで、赤色とはっきり区別できて、見やすい色として緑色が使われるようになったと考えられています。
緑色は、自然の中にある草や木の色で、私たちに安心感や安全なイメージを与えてくれます。 赤色の補色に近いので、並べて表示したときに見分けやすいというメリットもありました。
当時のガラスを色付けする技術で、赤色と緑色は比較的作りやすかったという事情も、もしかしたら影響したのかもしれません。
「黄信号」はどうしてできたの? 三色灯への進化が交通を安全に!
最初のころの信号機は、主に赤と緑の二色でした。
しかし、車の数が増えて、スピードも速くなってくると、二つの色だけでは対応が難しくなってきました。
特に、信号が赤から緑、緑から赤へと急に変わるとき、運転する人や歩いている人がすぐに対応できなくて、交差点で事故が起きやすくなる心配がありました。
この問題を解決するために登場したのが、「注意してね」と知らせるための中間の色、「黄色」だったんです。
黄色が仲間入り! 交通整理の新しいカタチ
黄色が信号システムに加わったのは、20世紀の初めごろのアメリカです。
自動車産業が盛んだったデトロイトのような都市では、交通渋滞や事故の増加が大きな問題になっていました。
そこで、もっと良い交通整理の方法が考えられるようになったのです。
1920年、デトロイトの警察官だったウィリアム・ポッツさんが、赤・黄・緑の三つの色を使った四方向信号機を考え出したと言われています(これにはいくつかの説があります)。
この三色灯の信号機が登場したことは、信号機の歴史の中でとても大きな出来事でした。
黄色が「注意」の色として選ばれたのにも、ちゃんとした理由があります。
黄色は、赤色と同じように比較的波長が長くて、遠くからでも見やすい色です。
色の光の成分で見ると、赤色と緑色の間にあって、どちらの色ともはっきり区別しやすいという特徴も持っています。
心理的には、黄色は注意を促し、気を引き締める色として感じやすいと言われています。
太陽の光や、工事現場などの警告の看板にもよく使われていますよね。
「何かが変わる前触れ」として、私たちの意識にインプットされている部分もあるのかもしれません。
黄色信号ができたことで、運転する人は信号が変わることを前もって知ることができ、スピードを落としたり止まったりする準備をする時間ができました。
これによって、交差点に無理に入ったり、急ブレーキで後ろの車に追突されたりする危険がぐっと減って、交通の安全とスムーズさが大きく向上したんです。
この三色システムは、とても効果が高かったので、あっという間に世界中に広まって、今の信号機の基本的な形になりました。
なぜ「青信号」って言うの? 緑色なのに「アオ」と呼ぶ日本の不思議な習慣
日本の信号機で「進んでよし」を意味する光の色は、国際的なルールと同じで「緑色」と決められています。 でも、私たちは普段の会話で「青信号」って普通に言いますよね。 この「緑色なのに青と呼ぶ」のは、外国の人から見るとちょっと不思議に思えるかもしれません。 しかし、これには日本の言葉の文化や歴史が深く関係しているんです。
「あお」は緑も含む? 日本語の色の世界の奥深さ
この謎を解くヒントは、日本語の「青(あお)」という言葉が持つ意味の広さにあります。 昔の日本では、今のように色を細かく分けて呼ぶ言葉があまり多くありませんでした。
「あお」という言葉は、緑色や藍色、ときには灰色や白に近い色まで、広い範囲の寒色系の色を指す言葉だったんです。
例えば、「青葉若葉」とか「青々とした山」、「青野菜」なんていう言葉は、どう見ても緑色のものを指しています。 でも、今でも自然に使っていますよね。 「青二才」とか「顔が青ざめる」という言葉も、未熟なことや血の気がない様子を「あお」で表現しています。
こんな言葉の背景に加えて、信号機が日本に入ってきたころの状況も影響していると考えられます。 明治時代に鉄道の信号が使われ始め、そのあと大正時代から昭和時代の初めにかけて道路の信号機が置かれるようになりました。
そのころの新聞や役所の書類で、緑色の信号灯を「青信号」と書いている例が見られたそうです。 これは、当時の人々にとって「緑」という言葉よりも「青」という言葉の方が、信号の色を表す言葉としてしっくりきたのかもしれません。
あるいは、色の三原色(赤・黄・青)という考え方が広まりつつあったので、緑を青の仲間として捉えることにあまり抵抗がなかった、という可能性も考えられます。
法律では、道路交通法施行令という決まりで、信号灯の色は「緑色」「黄色」「赤色」とはっきり決められています。
しかし、長い間の習慣として「青信号」という呼び方がみんなの間にすっかり定着していて、今でもこの呼び方が一般的です。
世界的には「グリーンライト」と呼ばれるものが、日本では「青信号」になる。 これは、言葉と文化が交わるところで見られる、とても興味深い例と言えそうですね。
色が心と体に働きかける? 信号機に使われる色の心理的・生理的な効果
信号機の色が赤・黄・緑(青)と決められたのは、ただ見やすいから、という物理的な理由だけではないんです。 これらの色が、私たちの心や体の働きにどんな影響を与えるかも、実はうまく考えられて使われています。
赤はドキドキ! 黄色は注意! 緑はホッとする! 色のパワーを解説
赤色 赤色は、私たちの体の交感神経という部分を刺激して、アドレナリンというホルモンがたくさん出るように促す効果があると言われています。
これによって、心臓のドキドキが速くなったり、血圧が上がったり、筋肉が緊張したりと、体はちょっと興奮したような、警戒したような状態になります。
この体の反応は、危ないことを感じ取って、すぐに避けるための行動をとる準備段階とも言えるんです。 「止まれ」という一番大事な指示を、本能的に危ないと感じさせる赤色で示すことは、運転する人や歩いている人の注意を強く引きつけて、素早い反応を促すのにとても効果的です。 赤色を見た瞬間に、意識しなくてもブレーキを踏む準備をしたり、立ち止まったりする行動が起きやすいのは、この色が持っている力のおかげなんですね。
黄色 黄色は、注意を促して、判断する力を高める効果があるとされています。 赤色ほど強い興奮作用はありませんが、目の神経を刺激して、集中力を高める働きがあると考えられています。 信号が黄色に変わることは、「もうすぐ赤になりますよ」という変化のお知らせです。
運転する人にとっては、「進むか、止まるか」という一瞬の判断が求められます。 このとき、黄色が持っている「気をつけて!」という意味合いが、より慎重な判断をする手助けになります。 黄色は、幸せな感じや明るい気持ちといった良いイメージとも結びつきますが、信号の場合は、その色の明るさや他の色との見分けやすさから、主に「警告」の色としての役割が強いです。
緑色(青色) 緑色は、自然の中にたくさんある色で、私たちの目にとって一番負担が少なくて、安らぎを感じさせる色だとされています。
副交感神経という部分に作用して、心臓のドキドキを落ち着かせたり、血圧を下げたり、筋肉の緊張を和らげたりと、リラックスする効果をもたらすと言われています。 信号機で緑色(青色)が「進め」を意味するのは、この色が持っている「安全」とか「安心」といった心に与えるイメージとぴったり合うからです。
緑色の光は、運転する人や歩いている人に対して、前は安全ですよ、安心して進んで大丈夫ですよ、というメッセージをはっきりと伝えてくれます。
このように、信号機の色は、それぞれの色が持っている体や心への影響を最大限に利用して、道路を使う人たちの行動をうまく導くようにデザインされています。 これは、人間工学とか色彩心理学といった専門的な知識が、実際の社会の安全システムに使われている良い例と言えるでしょう。
世界で通じる色のルール? 国際的な基準と信号機の進化
車や飛行機が発達して、外国との行き来が当たり前になった今の時代、交通ルールが世界で同じであることはとても大切です。
信号機の色とその意味についても、世界中で同じように理解できるようにするための取り組みが進められてきました。 その中心になっているのが、国際照明委員会(CIEと略されることもあります)という組織です。
CIEは、光や照明に関する世界的な基準を作っている機関で、信号の光の色の波長の範囲や明るさなど、具体的なことについても細かい決まりを設けています。
LED化やユニバーサルデザインで もっと見やすく誰にでも優しく
この国際的な基準のおかげで、世界の多くの国で、赤は「止まれ」、黄は「注意」、緑(または青に近い緑)は「進め」という基本的な意味が同じように使われています。
だから、外国で車を運転するときや、日本に来た外国人の旅行者さんが道路を使うときも、信号の意味を間違えることなく、安全に通ることができるんです。
ただし、国や地域によっては、信号機の形や並び方、点滅の仕方、歩行者用の信号の表示などに、その土地ならではの習慣やルールが見られることもあります。
最近では、信号機の光を出す部分にLEDというものが急速に使われるようになっています。 LEDは、昔の電球と比べて、使う電気がとても少なくて(約10分の1くらい)、寿命もずっと長い(約10倍以上)という特徴があります。
だから、電気代を節約できたり、取り替える手間が減ったりするのに役立っています。 LEDは、スイッチを入れてから光るまでの時間がとても速いので、パッとついてパッと消えるため、見やすさもアップします。
特定の色の光を効率よく出すことができるので、よりくっきりとしたきれいな色が出せて、昼でも夜でも、天気が悪いときでも見やすさが向上しています。
さらに、色の見え方に違いがある人たちにも配慮した、ユニバーサルデザインの信号機の開発も進んでいます。
例えば、色の違いだけではなくて、光る部分の形(赤は四角、黄は三角、緑は丸など)を変えたり、光る位置を変えたり、信号の中にマーク(人の形やバツ印、矢印など)を表示したりすることで、情報を補う工夫がされています。
これによって、より多くの人が信号の意味を正しく理解して、安全に道路を使える社会を目指しているんですね。
未来の信号機はどうなるの? 進化する技術とこれからの交通システム
信号機の技術は、今もどんどん進化しています。
特に、ITS(アイティーエス)と呼ばれる高度道路交通システムの発展は、信号機の役割を大きく変えようとしています。
将来的には、信号機がただ決まった順番で光を変えるだけではなくて、そのときの交通状況や車の情報を読み取って、一番良いタイミングで信号をコントロールする「感応式信号システム」がもっと賢くなっていくと考えられます。
AIや通信技術で信号機がもっと賢く! 自動運転の時代には?
例えば、交差点に付いているセンサーやカメラが、車が近づいてきたり道が混んでいたりするのを察知します。 そして、AI(人工知能)がその情報を分析して、信号の青時間を自動で調整することで、車の流れをスムーズにして、無駄な待ち時間を減らす試みが進んでいます。
救急車や消防車のような緊急車両が近づいてきたときに、優先的に青信号にするシステムも実際に使われています。
さらに、V2I(ブイツーアイ)という車と信号機が直接情報をやり取りする通信技術が発達することで、運転する人は車の画面を通じて、先の信号の色や残り時間といった情報を前もって受け取ることができるようになりつつあります。
これは、安全運転を助けるだけではなくて、無駄なアクセルやブレーキを減らして、車の燃費を良くすることにもつながると期待されています。
究極的には、全ての車が自動で運転する社会が実現すれば、道路にある信号機そのものが必要なくなるかもしれない、とも言われています。
全ての車がインターネットでつながって、大きなコンピューターや車同士の通信でうまくコントロールされれば、交差点での交通整理も画面の中だけでできるようになるかもしれません。
しかし、まだ人間が運転する時代や、歩いている人や自転車との共存を考えると、目で見て情報を伝える信号機の役割は、しばらくの間は、やはり重要であり続けるでしょう。
スマートシティという未来の街づくり構想の中では、信号機はただ交通を整理する装置ではなくて、街全体のエネルギー効率を良くしたり、環境への負担を減らしたり、住んでいる人たちの生活の質を上げるのに役立つ、いろいろな機能を持った設備として考えられる可能性もあります。
例えば、信号機に周りの環境を調べるセンサーや情報を見せる画面、Wi-Fiの基地局などが一緒になることも考えられます。
まとめ:いつもの信号機に隠された色の科学と安全への願い
信号機の「赤・黄・青(緑)」という三つの色は、パッと見ると単純な色の組み合わせに思えるかもしれません。
しかし、その裏には、人間が長い時間をかけて築き上げてきた安全への強い願い、科学的な知識の積み重ね、そして文化的な感覚がぎゅっと詰まっています。
危険を知らせる世界共通の「赤」、注意を促して判断を助ける「黄色」、そして安全と進行を優しく示す「緑(青)」。
これらの色は、それぞれの特徴が一番よく活かされる形で選ばれて、私たちの意識しないレベルにまで働きかけて、毎日の交通安全を支えてくれているんですね。
鉄道が生まれたころから、未来のスマートシティ構想に至るまで、信号機はその時代ごとの新しい技術を取り入れながら、その役割を進化させてきました。
しかし、その基本にある「色」という、一番わかりやすい情報伝達の方法の大切さは、今も昔も変わっていません。
次にあなたが交差点で信号待ちをするときには、ぜひ一度、その光の色が持っている深い意味や、そこに込められたたくさんの人たちの知恵と努力に思いを巡らせてみてください。
それは、ただの色が変わるというだけではなくて、私たちの社会が作り上げてきた安全への願いのしるしとして、新しい気持ちを与えてくれるかもしれません。
この記事が、信号機の色という身近なテーマを通じて、科学や歴史、文化への興味を深めるお手伝いになり、そして何よりも毎日の交通安全への意識を高めるきっかけになれば、とても嬉しいです。
【免責事項】
当サイトで提供する情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、専門的なアドバイスを提供するものではありません。
記事の内容の正確性については可能な限り努力をしていますが、その内容を完全に保証するものではありません。
当サイトの情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
情報の利用に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

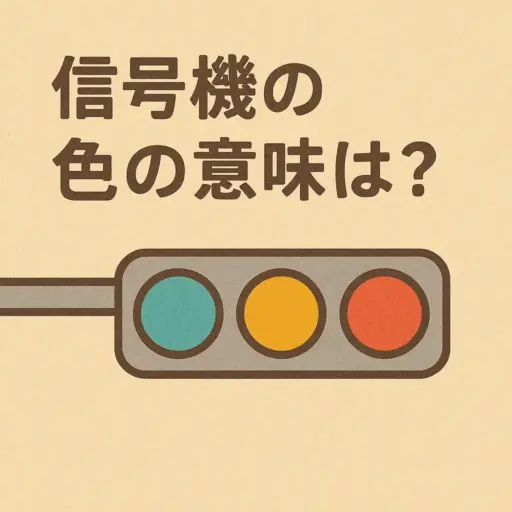

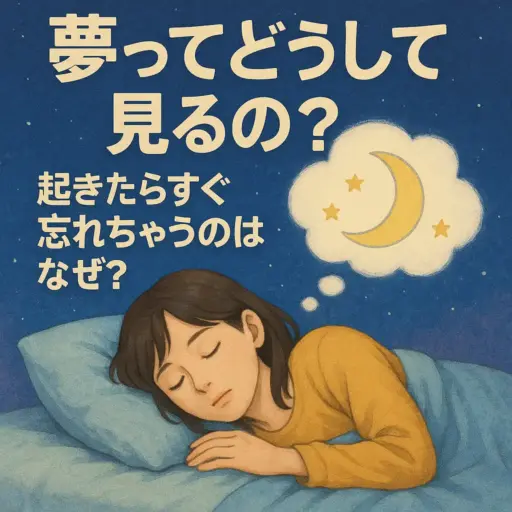

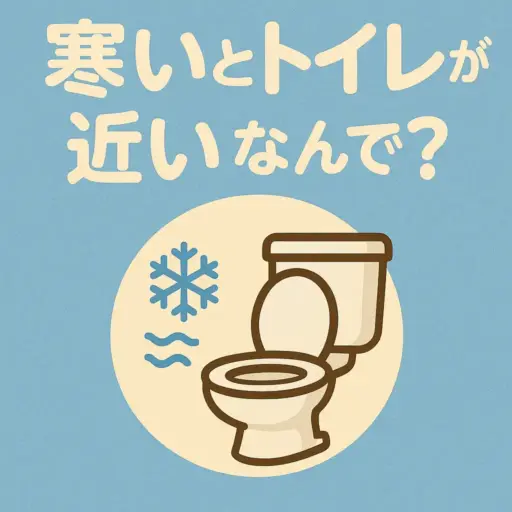

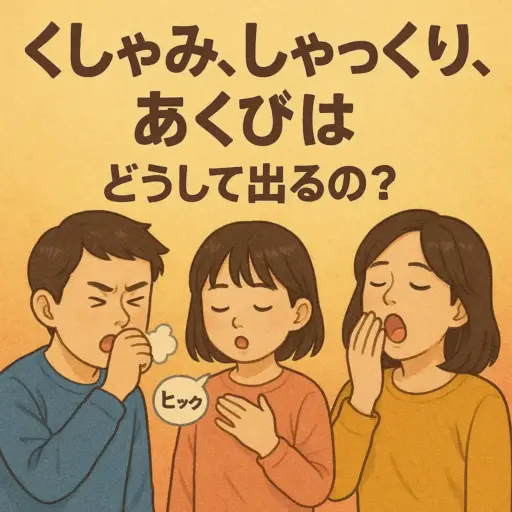
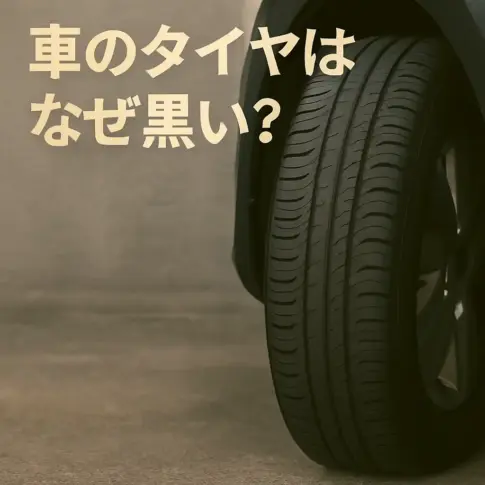



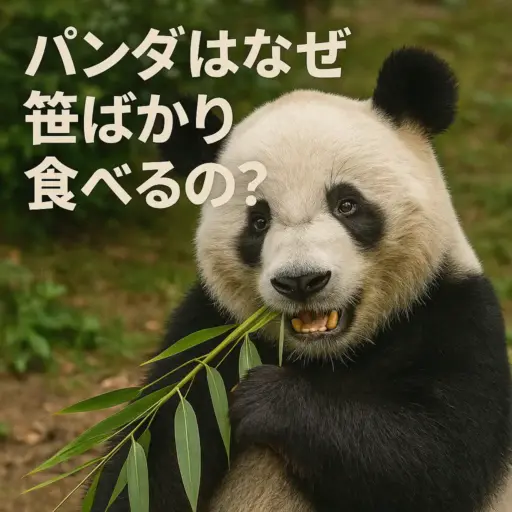


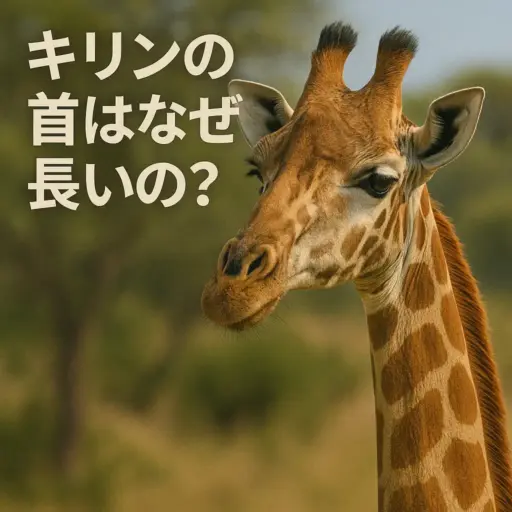


コメントを残す